はじめに
名古屋のシンボル、金色に輝く金鯱(きんのしゃちほこ)。
その美しい姿の裏に、江戸時代の藩財政を巡る壮絶なドラマが隠されていることをご存知でしょうか。
徳川家康が天下に権力を誇示するために設置した純金215kgの金鯱は、やがて尾張藩の「金庫」として何度も鋳直され、その輝きを失っていきました。
権威の象徴が財政難により切り売りされる過程は、現代の私たちにも重要な教訓を与えてくれます。
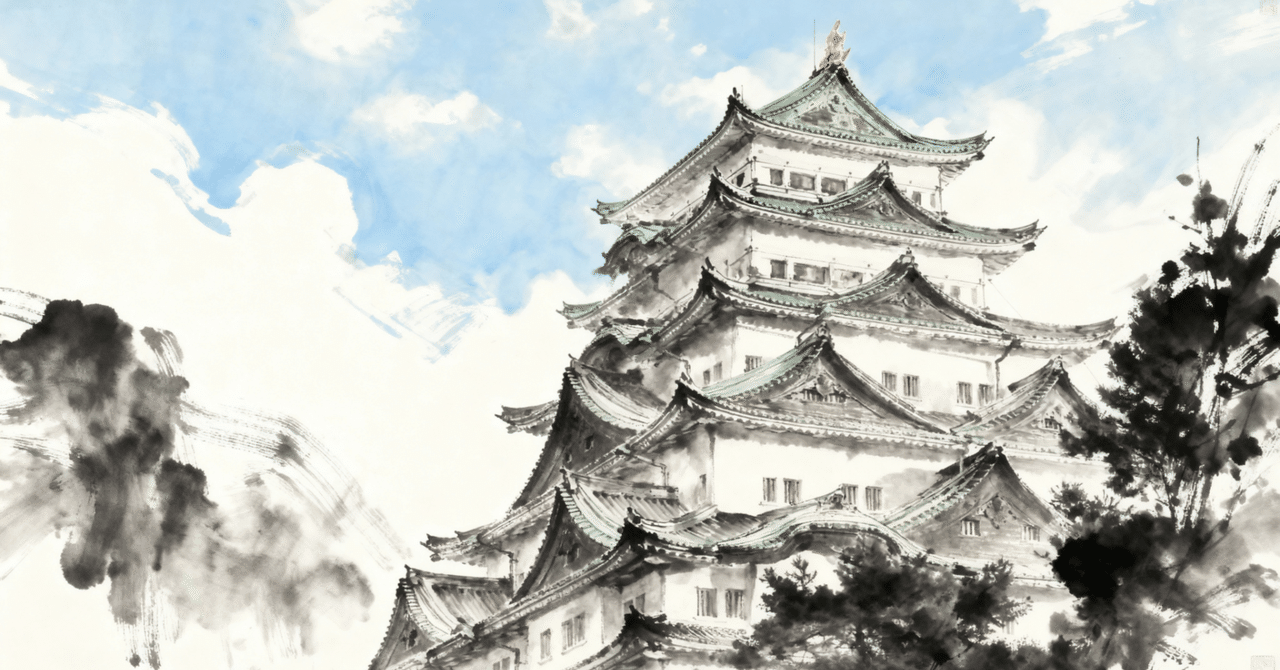
目次
- 黄金の権威:慶長期の金鯱誕生
- 御三家筆頭の苦悩:慢性的な財政危機
- 禁断の決断:享保期から弘化期の改鋳
- 失われた輝き:ブランド毀損の代償
- 教訓:シンボル資産の現金化がもたらすもの
1. 黄金の権威:慶長期の金鯱誕生
1612年(慶長17年)、徳川家康の命により名古屋城天守が完成しました。
その最上部に設置された一対の金鯱は、単なる装飾ではありませんでした。
檜の芯材を鉛板、銅板、そして金板で順次包む精巧な多層構造で、慶長大判1,940枚分、純金にして約215.3kgもの黄金が使われたのです。
これは現代の金相場で換算すると約14億円以上に相当する莫大な投資でした。
雄は高さ約2.57m・鱗194枚、雌は高さ約2.51m・鱗236枚で構成され、錺屋(かざりや)と呼ばれる金細工専門職人が製作を担当しました。
家康はこの圧倒的な富の可視化により、徳川家の権威が軍事力だけでなく経済力によっても裏打ちされていることを天下に示したのです。
金鯱の輝きは、御三家筆頭としてこの城に入る徳川義直の格式を全国の大名や民衆に知らしめる、無言のプロパガンダ装置として機能しました。
2. 御三家筆頭の苦悩:慢性的な財政危機
徳川御三家の筆頭として最高の格式を誇った尾張藩ですが、その内情は江戸時代中期から深刻な財政難に苦しんでいました。
表高61万9500石、実質90万から100万石とも推定される大藩でありながら、なぜこのような事態に陥ったのでしょうか。
第一の要因は、御三家筆頭という格式維持のための莫大な支出です。
藩主の江戸在住による二重の経費負担、参勤交代などの幕府賦役は大名の年間支出の70〜80%を占めたという研究もあります。
第二に、度重なる天災や寺社建立費用が財政を圧迫しました。
第七代藩主・徳川宗春の時代には、規制緩和と文化振興策により経済活性化を図りましたが、支出が急増します。
1738年には差引14万両の大赤字、同年の金米両部門支出総額は42万両に達し、前任の継友期の35万両から大幅な増加となりました。
その後も天災による庄内川氾濫、寺社建立費用、災害復旧費などで財政難が継続し、1788年には累積債務が215,000両に到達しました。
第九代藩主・徳川宗睦は市中の富商56人から金5000両を調達し、幕府に2万両の公金拝借を申請する事態となります。
倹約令や富商からの借入など、あらゆる伝統的な財政手段は限界に達していたのです。
3. 禁断の決断:享保期から弘化期の改鋳
追い詰められた尾張藩が最後に目を向けたのが、藩の権威の象徴である金鯱でした。
改鋳は表向き「天守修理」「保存措置」として位置づけられましたが、実質的には金の含有量を段階的に削減し、取り出した金を藩財政に充当する苦肉の策だったのです。
享保期(1726〜1730年)
最初の改鋳では、錺屋六左衛門が担当し、頭部と背鰭下方の鱗を作り直し、芯材を一部交換しました。
修理手順は「真木を鉛板で包み鋲釘を打つ→上に銅板を載せ漆を付けて鋲打ち→金を着せる→上下の鰭をかすがいで締める→鱗を筋鉄物で打ち、銯で締める」という工程でした。
この時点で既に『金城温古録』には「金を薄く打ったため、品質が大いに悪くなった」という記録が残っています。
享保期は第六代藩主・継友の質素倹約政策により財政再建に成功した時期であり、この改鋳は主に天守修理費の捻出と保存措置としての側面が強かったと考えられます。
文政期(1826〜1827年)
財政が最も逼迫した時期に実施された二回目の改鋳では、状況は深刻化しました。
文政9年9月に開始され、翌年2月に完了したこの改鋳の最大の特徴は、金の品位を大幅に低下させたことです。
『金城温古録』の記述は明確です。「享保の修理時、金を薄く打ったため、大いに悪しく、文政ではさらに薄く打ったため、約十年で早くもめくれるようになり、さらに銀を大分混ぜて打ったため性が悪くなった」。
つまり文政修理では、金板をさらに薄く延ばし、金に銀を大量に混入させることで、金の使用量を大幅に削減し、差額を藩財政に充当したのです。
文政10年正月14日の『尾州御留守日記』には「天守鯱修復につき、下御庭から見上げる機会を作事方が設けようとしたが、人が多く中止にいたった」との記述があり、改鋳作業に対する公衆の高い関心が窺えます。
しかし、この改鋳の結果は悲劇的でした。
金を極端に薄くし、銀を大量混入させたため、金板の接着力と耐久性が著しく低下し、わずか約20年後に鱗がめくれ落ちる事態となりました。
弘化期(1846年)
三回目の改鋳は緊急事態として実施されました。
『青窓紀聞』には「真木の故障はなく、金の着せ方が不適切だったためめくれ落ちた」と記録されています。
さらに深刻なのは、掃除担当者の中に、剥がれ落ちた金を届け出ずに私的に売却した者がいたという事実です。
シンボル資産の品質劣化が職員の不正行為を誘発するという副次的な問題も発生していました。
1852年には四回目の改鋳が実施され、改鋳の頻度増加は財政難の継続を示しています。
4. 失われた輝き:ブランド毀損の代償
改鋳による金の純度低下は、金鯱の輝きを著しく鈍らせました。
創建時の黄金色とは程遠い、くすんだ色合いになった金鯱を再び天守に掲げることは、藩の財政的困窮と権威の失墜を自ら天下に公言するに等しいものでした。
城下の人々の間では「近来の修復から色が悪い」という評判が広まります。
藩は窮余の策として、金鯱を金網で覆い隠す措置を講じました。
表向きは「鳥害対策」や「盗難防止」とされましたが、実際は品質劣化の隠蔽でした。
しかし、この試みは逆効果となりました。
金網は「何かを隠している」という印象を強め、藩の財政難と窮状を露呈する結果となった可能性があります。
徳川御三家筆頭としての権威は、もはや外見を取り繕うことでしか維持できないほど空洞化していたのです。
改鋳で得られた資金の具体的な額は、一次史料では確認されていません。
『金城温古録』編纂者・奥村得義の推測が後世の『名古屋城史』で定説化しましたが、一次史料による裏付けは不十分です。
しかし、1848年には幕府から10万両の貸与を受けるなど、金鯱改鋳だけでは財政再建が不可能であることが明らかになりました。
5. 教訓:シンボル資産の現金化がもたらすもの
名古屋城金鯱の改鋳は、シンボル資産の現金化が持つ多面的な影響を示す歴史的教訓です。
短期的には一定の収入をもたらした可能性がありますが、長期的にはブランド毀損、公衆の信頼低下、組織規律の弛緩という代償を伴いました。
品質を劣化させた金鯱は、わずか20年で物理的破綻を招き、かえって修理費用が増大するという悪循環を生みました。「改鋳」という名目での段階的な資産収奪は、一時的な財政緩和の代わりに、藩の権威と象徴性という無形資産を毀損したのです。
明治4年(1871年)、金鯱は尾張徳川家から宮内省に献上され、湯島聖堂博覧会やウィーン万国博覧会で展示されました。
明治11年に名古屋に返還され、翌12年2月に再設置されましたが、1945年の名古屋空襲で天守とともに焼失します。
1959年に市民の熱意により二代目が再建されました。
現在の金鯱は18金で製作され、雄は高さ2.621m・重量1,272kg(18金44.69kg)、雌は高さ2.579m・重量1,215kg(18金43.39kg)です。金の厚さは0.15mm、鱗数は雄112枚・雌126枚と、創建時とは異なる仕様となっています。
現代の企業や組織にとっても、この事例は重要な示唆を持ちます。
ブランド・評判・象徴といった無形資産は、短期的な財務的利益のために安易に毀損すべきではありません。
一度失われた信頼の回復には長期間を要します。
財政難の根本原因に対処せずに、シンボル資産を切り売りする対症療法は、問題を先送りし悪化させるだけなのです。
いかなる強固な権威の象徴も、それを支える経済的実盤が失われれば、その輝きを保つことはできません。
尾張藩の金鯱改鋳は、権力の象徴が財政難により段階的に毀損されていく過程を、一次史料により検証可能な形で示す貴重な歴史的教訓なのです。
参考文献
- 朝日美砂子「名古屋城天守金鯱 過去と今」名古屋城調査研究センター研究紀要第6号(2025年)
- 『金城温古録』(奥村得義編、1842-1902年編纂、名古屋市蓬左文庫蔵)
- 『青窓紀聞』(水野正信、1805-1855年編纂、名古屋市蓬左文庫蔵)
- 『編年大略』『尾藩世紀』(徳川林政史研究所蔵)
- 『御天守鯱木地仕口寸尺之図』(文政10年作成、名古屋城総合事務所・宮内庁宮内公文書館蔵)
- 『尾州御留守日記』(徳川林政史研究所蔵)
- 名古屋城公式ウェブサイト(https://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/)
- Wikipedia「尾張藩」「名古屋城」
- 三菱マテリアル「金の博物誌」

コメント