はじめに
「日本三大悪女」の一人として名高い北条政子。夫の愛人の家を破壊し、実の息子を追放し、朝廷に弓を引いた女性――そんなイメージで語られることの多い彼女ですが、果たしてそれは真実なのでしょうか。
実は、政子が生きた鎌倉時代の人々は、彼女を「有能な政治家」として評価していました。
「悪女」というレッテルが貼られたのは、数百年後の江戸時代のこと。
時代によって評価が180度変わってしまった北条政子の実像に、現代の視点から迫ります。
👇noteやYouTubeでも紹介してますのでこちらもご覧ください

目次
- 北条政子とは何者か
- なぜ「悪女」と呼れるようになったのか
- 鎌倉時代の女性は今より自由だった
- 政治家としての冷徹な決断
- 承久の乱での伝説の演説
- 歴史評価の変遷が教えてくれること
- まとめ
- 参考文献
1. 北条政子とは何者か
北条政子は1157年頃、伊豆の地方豪族・北条時政の娘として生まれました。
父の反対を押し切って、流罪となっていた源頼朝と結婚。
頼朝が鎌倉幕府を開くと、将軍の正妻として重要な地位を占めます。
1199年に頼朝が急死すると、政子は出家して尼となりましたが、政治の世界から引退したわけではありませんでした。むしろ「尼将軍」として、息子たちを将軍に立てながら、実質的に幕府を運営していったのです。
彼女の最大の功績は、1221年の承久の乱で幕府軍を勝利に導いたこと。
後鳥羽上皇が幕府打倒を図った際、動揺する武士たちを前に演説し、約19万人を動員して朝廷軍を破りました。
これにより武家政権の基盤が確立され、以後150年続く鎌倉幕府の礎が築かれたのです。
2. なぜ「悪女」と呼ばれるようになったのか
政子が「悪女」と呼ばれるようになった理由は、主に三つのエピソードによります。
第一に、激しい嫉妬心。
1182年、妊娠中の政子は、夫・頼朝が愛人の亀の前を囲っていることを知り激怒。
家臣に命じて亀の滞在していた館を破壊させました。
さらに別の愛人が男児を産んだ時には、出産祝いをすべて中止させ、愛人を追放しています。
第二に、実の息子への非情な対応。
1203年、長男・頼家が将軍として問題行動を繰り返すと、政子は父や弟と協力してクーデターを起こし、頼家を追放。頼家の幼い息子(政子の孫)も含めて一族を滅ぼし、次男・実朝を将軍に立てました。
第三に、実父の追放。
1205年には、父・時政が実朝の排除を企てていることを知ると、今度は実の父を強制的に引退させ、伊豆へ追放しました。
これらの行動は、江戸時代の儒教的価値観では「女性としてあるまじき行為」と見なされました。
夫に従順であるべき、子への愛情を最優先すべき、父に孝行すべき――そうした規範に真っ向から反する政子の姿は、「悪女」の典型として語られるようになったのです。
3. 鎌倉時代の女性は今より自由だった
しかし、政子の行動を理解するには、当時の社会背景を知る必要があります。
実は鎌倉時代初期の女性は、後の時代よりもずっと大きな権利を持っていました。
財産権が認められていた。
女性も土地を相続し、所有し、自由に処分することができました。幕府の法律『御成敗式目』にも、女性の財産権を保障する条項が複数含まれています。
政治的役割も担っていた。
武士の妻は単なる家庭の管理者ではなく、夫が不在の時には家の代表として領地を統治し、訴訟の当事者となることもありました。「地頭職」という重要な役職を女性が務めた例も数多く確認されています。
出家は権力への道だった。
夫の死後に出家することで、女性は特定の家への帰属から解放され、より公的な立場を得ることができました。政子の「尼将軍」という称号は、宗教的権威と世俗的権力を結びつけた特異な地位を象徴しています。
つまり、政子の権力は、当時の社会が女性に許容していた活動範囲の中で、最大限に発揮されたものだったのです。
4. 政治家としての冷徹な決断
政子の行動を「悪女」と断じる前に、それが政治的にどのような意味を持っていたかを考える必要があります。
亀の前事件の政治的側面。
愛人の館を破壊した行為は、単なる嫉妬ではありませんでした。
当時、正妻の地位は絶対的なものではなく、他の女性との子が後継者になる可能性もあったのです。
政子は自分の息子の相続権を守るため、正妻としての地位を示威する必要があったのです。
頼家排除の合理性。
長男・頼家を追放した判断も、個人的な感情ではなく政治的な計算に基づいていました。
『吾妻鏡』によれば、頼家は「民の生活を省みず、酒食に溺れ」るなど、統治者として不適格でした。
さらに頼家の外戚である比企一族と、政子の実家である北条一族の間で激しい権力闘争が起きており、どちらかが滅びる状況でした。政子は幕府の安定のため、北条側に立つ決断をしたのです。
父の追放も必要だった。
実父・時政の追放も同様です。
時政が将軍・実朝の暗殺を企てていることを知った政子は、幕府を守るため父よりも弟・義時を選びました。
こうした決断は、同じ状況に置かれた男性の権力者なら「優れた政治的判断」と評価されるでしょう。
徳川家康も主君の一族を滅ぼし、源頼朝も実弟を追討しています。
しかし、男性の場合は「戦略家」と呼ばれ、政子の場合だけ「非情な悪女」と呼ばれる――ここに明確なジェンダーバイアスがあるのです。
5. 承久の乱での伝説の演説
政子の政治家としての頂点は、1221年の承久の乱でした。
後鳥羽上皇が北条義時追討の命令を出すと、鎌倉の武士たちは動揺します。
天皇の命令に逆らえば「朝敵」となってしまう――そんな不安が広がる中、政子は御家人たちを召集し、演説を行いました。
『吾妻鏡』によれば、その内容はこうです。
「故・頼朝公が朝敵を征伐し、幕府を開いて以来、あなた方が授かった官位も領地も、その恩は山よりも高く海よりも深い。今こそその恩に報いる時です。名を惜しむ者は、三代将軍の遺跡を守りなさい」
この言葉に武士たちは感動し、涙を流して結束。
約19万人が動員され、わずか1か月で朝廷軍を破りました。
ただし、この演説については史料によって描写が異なります。
『吾妻鏡』では安達景盛が代読したとされますが、『承久記』では政子自身が語ったとされています。
どちらが真実かは不明ですが、いずれにせよ尼将軍の言葉が幕府を救ったことは間違いありません。
6. 歴史評価の変遷が教えてくれること
政子の評価は時代とともに劇的に変化しました。
13世紀(同時代): 『吾妻鏡』は政子を「鎌倉殿」という将軍の称号で呼び、僧侶・慈円は「女性が活躍する日本国」と肯定的に評価しました。
14〜16世紀(室町時代): この時期も政子への評価は比較的高く、「悪女」という特徴づけはまだ確立していませんでした。
17〜19世紀(江戸時代): 徳川幕府が儒教思想を採用し、「女性は父・夫・子に従うべき」という価値観が支配的になると、政子の評価は急落。「日本三大悪女」の一人として定着しました。
20世紀後半〜現代: 1964年に作家・永井路子が『北条政子』を発表し、フェミニスト史学の視点から政子を再評価。近年では、Michigan State大学のEthan Segal教授らが「政子は日本唯一の女性将軍だった」として研究を進めています。
この変遷が示すのは、「悪女」という評価が歴史的事実ではなく、後世のイデオロギーによって作られたものだということです。
7. まとめ
北条政子は、愛する夫のため、幼い息子たちのため、そして鎌倉幕府という新しい政治体制のために、時に激しく、時に冷徹に行動した政治家でした。
彼女の嫉妬は正妻としての地位を守るための戦略であり、息子や父への対応は幕府存続のための苦渋の決断でした。
承久の乱での演説は、武家政権の正統性を守り抜いた歴史的瞬間でした。
これらの行動が「悪女」として非難されてきたのは、主に江戸時代の儒教的価値観によるものです。
同じ行動をした男性権力者は「優れた統治者」と評価されるのに、女性の場合だけ「非情」「嫉妬深い」と道徳的に断罪される――この二重基準こそが、歴史叙述におけるジェンダーバイアスの典型例なのです。
北条政子の生涯は、私たちに問いかけています。
歴史上の人物を評価する時、私たちは本当に客観的でいられるのか。
性別によって、同じ行動が全く違う評価を受けることはないか。
そして、「常識」とされる価値観は、本当に普遍的なものなのか――。
彼女の実像を知ることは、歴史をより複眼的に見る力を養うことにつながるでしょう。
参考文献
一次資料
- 『吾妻鏡』(鎌倉幕府公式編年記、1266年頃成立)
- 慈円『愚管抄』(1220年頃)
- 『承久記』(1230年頃)
- 国立公文書館デジタルアーカイブ所蔵『吾妻鏡』画像
二次資料・研究論文
- 山本みなみ『史伝 北条政子』2022年
- 野口華世「北条政子と牧の方:ジェンダーの視点から」『研究紀要』38号、京都女子大学宗教・文化研究所、2025年
- 今井雅晴『鎌倉北条氏の女性たち』教育評論社、2022年
- 永井路子『北条政子』文藝春秋、1964年
- Hitomi Tonomura, Anne Walthall, Wakita Haruko (eds.), Women and Class in Japanese History, University of Michigan Press, 1999
- Ethan Segal, “Rethinking Women’s Roles in Early Medieval Japan: Was Hojo Masako Japan’s Only Female Shogun?” 講演シリーズ、2017-2018年
ウェブ資料
- 北条政子 – Wikipedia (https://ja.wikipedia.org/wiki/北条政子)
- Encyclopedia.com: Hojo Masako (1157–1225)
- Japan Reference: Bio – Hōjō Masako (1157-1225)
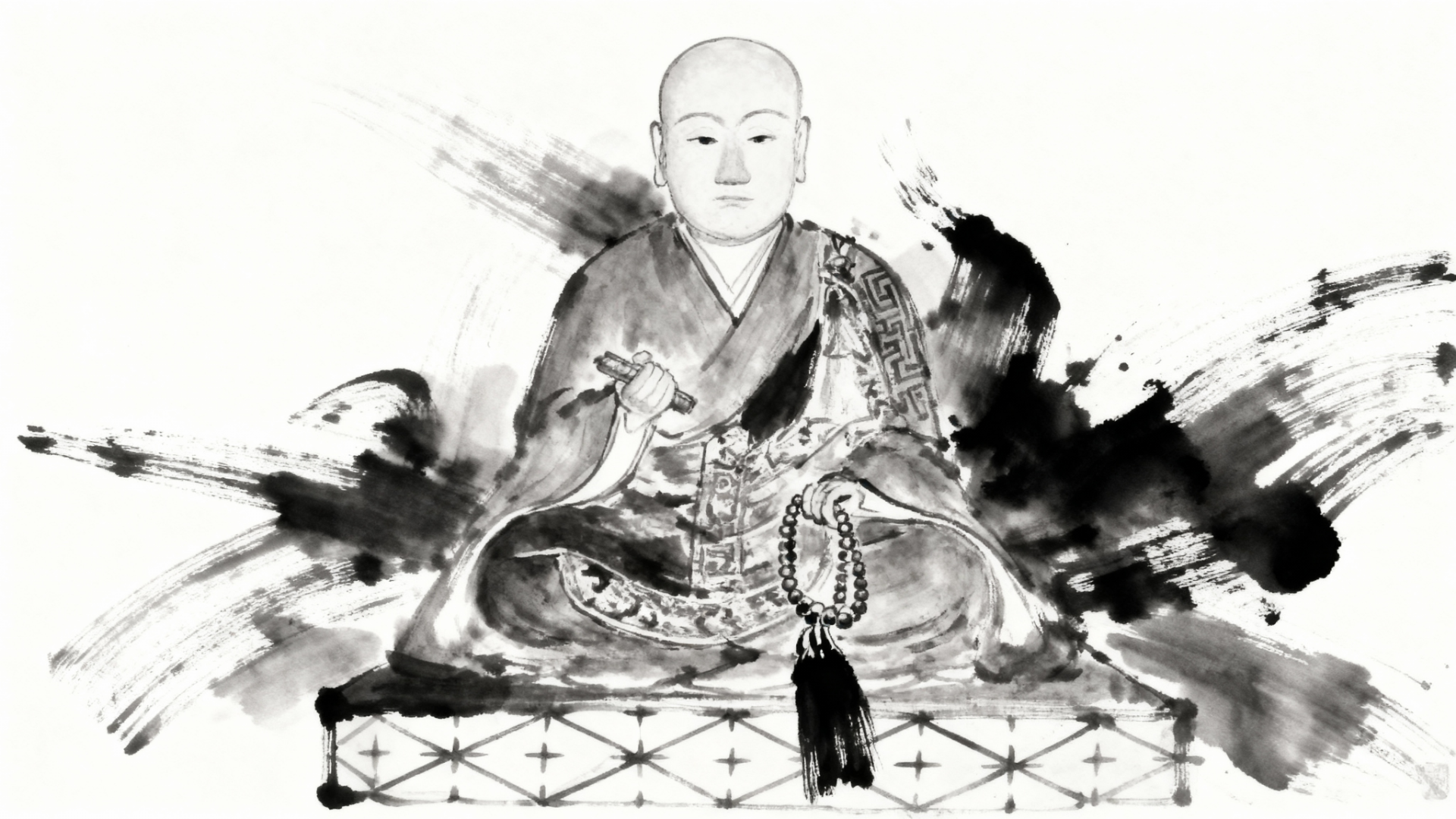
コメント