はじめに
将来を約束された名家の跡取りが、なぜすべてを投げ打って僧侶になったのでしょうか。
江戸時代、厳しい身分制度の中で、子供から大名まで分け隔てなく接し、一生を草庵で過ごした禅僧がいました。
良寛(りょうかん)―彼の生き方は、今も多くの人々の心を打ち続けています。
この記事では、史料に基づいて良寛の実像に迫ります。
👇noteで深掘りした記事も書いてます。よろしければこちらもご覧下さい
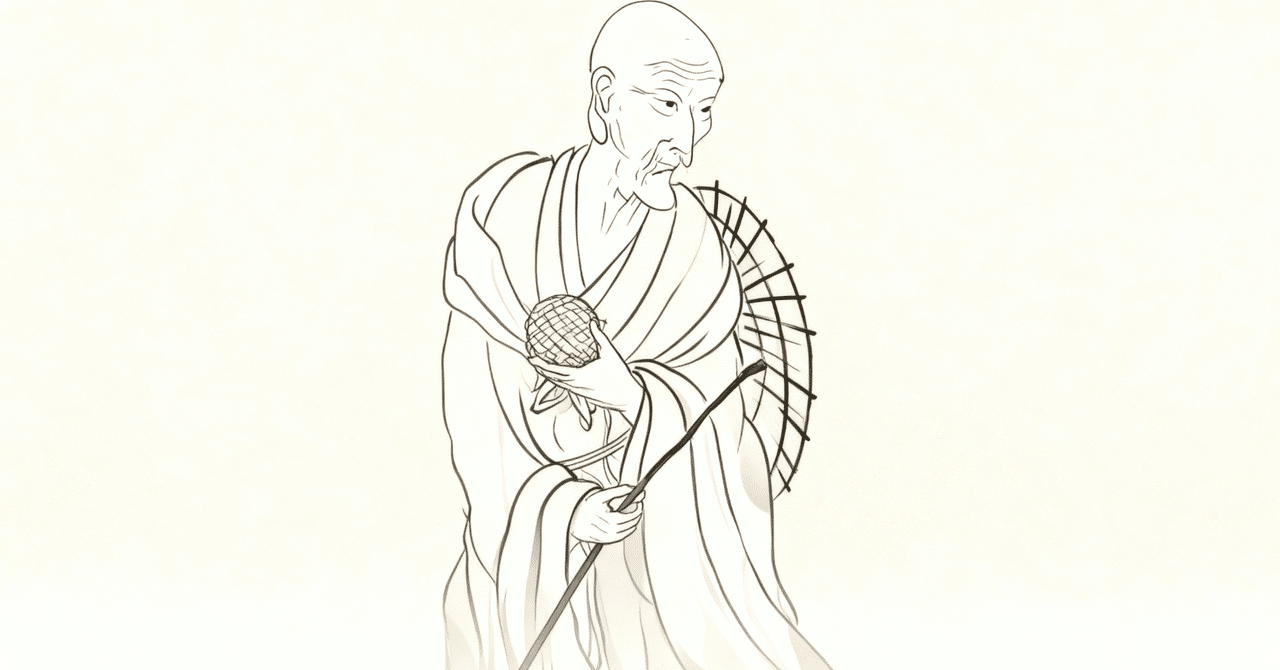
目次
- 約束された未来を捨てた18歳
- 12年間の厳しい修行
- 五合庵での清貧な暮らし
- 誰とでも対等に―良寛の人間関係
- 晩年と貞心尼との出会い
- 現代に残る良寛の教え
- 参考文献
約束された未来を捨てた18歳
良寛は1758年、越後国出雲崎の名主・山本家の長男として生まれました。
名主とは村の責任者で、年貢の徴収や争いの調停など、幕府の行政を担う重要な役職です。
出雲崎は佐渡金山の金銀荷揚げ港として栄えた天領(幕府直轄地)であり、山本家はその中心的存在でした。
父・以南は俳人としても知られる文化人で、良寛は13歳から儒学を学びます。
将来は家督を継ぎ、地域を支える立場が約束されていました。
しかし、1775年、18歳で名主見習いに就いた良寛は、わずか46日間でその職を放棄してしまいます。
当時は天災や凶作が続き、社会不安が広がっていた時代でした。
名主の仕事は、飢えた人々の争いを調停し、時には処罰にも立ち会う過酷なものだったのです。
良寛は突然家を出て、近くの光照寺で出家します。
出家の理由について、良寛自身は多くを語っていません。
ただ自作の歌に「世を捨てし 捨てがひなしと 世の人に 言はるなゆめ(出家を無駄にするなと言われるな)」という父の言葉を残しており、父は最終的に出家を許可したことが分かります。
12年間の厳しい修行
1779年、22歳の良寛は備中国玉島(現在の岡山県倉敷市)の円通寺を訪れた国仙和尚に出会い、弟子入りを志願しました。
円通寺は曹洞宗の厳格な修行道場で、「一日作らざる者は、一日食わず」という原則のもと、労働と坐禅を中心とした修行が行われていました。
修行中の1783年、26歳の時に母が亡くなりますが、良寛は帰郷を許されませんでした。
それほど修行は厳しいものだったのです。
1790年、33歳で国仙和尚から「印可の偈」を授けられます。
これは修行完了の証明であり、正式な僧侶として認められたことを意味します。
国仙和尚は良寛に寺の住職を任せようとしましたが、良寛はこれを辞退しました。
翌年、師が亡くなると、良寛は寺を継ぐことなく諸国行脚の旅に出ます。
これが良寛の生涯を貫く基本姿勢となりました。
五合庵での清貧な暮らし
1795年、父が京都で入水自殺したという報せが届きます。
1796年、39歳で越後に帰郷した良寛は、実家には戻らず各地の庵を転々としました。
1800年頃から、良寛は国上山の五合庵に住み始めます。
ここで約20年間、托鉢による清貧な生活を送りました。
六畳ほどの簡素な建物で、入口は菰(こも)、床は土間に筵(むしろ)という極めて質素な暮らしです。
良寛は毎日托鉢に出かけ、最低限の食と衣で満足していました。
自身の和歌「たくほどは 風がもてくる 落ち葉かな」が示すように、必要なものは自然が与えてくれるという境地に達していたのです。
書については生前から高い評価を受けていましたが、高名な人物からの依頼は断り、子供からの依頼には喜んで無償で応じるという姿勢を貫きました。
誰とでも対等に―良寛の人間関係
良寛の特徴は、身分に関係なく人々と交流したことです。
ただし、史料を検証すると、実際の交流相手は主に地方名士層(豪農・商人・医師・文人)でした。
これは良寛自身が名主の家柄出身であることを考えれば自然な人間関係だったと言えます。
最も有名なのは子供たちとの交流です。
良寛は手毬や草相撲をして遊び、凧に「天上大風」と書いてあげたという逸話が残っています。
「この里に手まりつきつつ子どもらと遊ぶ春日は暮れずともよし」という歌からも、子供を深く愛していたことが分かります。
また、困った人を助けるエピソードも伝えられています。
庵に盗賊が入った時、盗むものがないのを哀れんで自分の布団を差し出したという話は、良寛の無欲な人柄を象徴しています。
長岡藩主から寺の住職を依頼されても断り、生涯を通じて特定の寺院や役職に就くことはありませんでした。
制度化された権威を徹底して拒み続けたのです。
晩年と貞心尼との出会い
1816年、59歳で五合庵を出て、乙子神社の草庵に移ります。
さらに1826年、69歳で豪農・木村家の離れに移住しました。
1827年、長岡藩士の娘で尼僧となった貞心尼(当時30歳)が良寛を訪ねます。
40歳の年齢差を超えて、二人は和歌を通じた深い精神的交流を始めました。
これらの歌は貞心尼が編纂した『蓮の露』として現存しています。
1828年には三条地震が発生し、良寛は被災した子供たちに見舞いの書簡を送りました。
有名な「災難に逢う時節には災難に逢うがよく候。死ぬ時節には死ぬがよく候」という言葉は、運命を受け入れる良寛の人生観を示しています。
1831年1月6日、良寛は木村家で74年の生涯を閉じました。
臨終には弟の由之と貞心尼が立ち会ったとされています。
現代に残る良寛の教え
良寛が遺したのは、和歌約1,400首、漢詩約450首、書2,000点以上です。
その作品は技巧よりも真情の表現を重視し、「我が詩は是れ詩に非ず 心中の物を写さずんば 多しと雖も復た何をか為さん」という言葉に、その芸術観が表れています。
良寛の思想の核心は、立身出世の否定、清貧への肯定、真情の表現、慈愛の実践にあります。
「生涯 立身に懶(ものう)く 騰々として天真に任す」という漢詩が示すように、出世には気が進まず、自然の真実に身を任せる生き方を選びました。
現代でも良寛は、物質的な豊かさより精神的な自由を重んじた人物として高く評価されています。
川端康成はノーベル文学賞受賞式で良寛の和歌を紹介し、「日本人の精神の典型」と讃えました。
競争や効率が重視される現代社会において、良寛の「求めない生き方」は、私たちに大切なことを思い出させてくれます。
地位や財産を超えたところにある本当の豊かさとは何か―良寛の生涯は、今もその問いを投げかけ続けているのです。
参考文献
- 『良寛全集』東郷豊治編、東京創元社、1959年
- 『良寛禅師奇話』解良栄重、野島出版、1979年
- 『蓮の露』貞心尼編、1831年以降編纂
- 燕市「良寛略年譜」、燕市教育委員会、2021年
- 良寛記念館公式情報、出雲崎町
- 「file-10 永遠の良寛」新潟文化物語、新潟県文化振興課
- 「良寛のこころ」新潟県友会、2024年
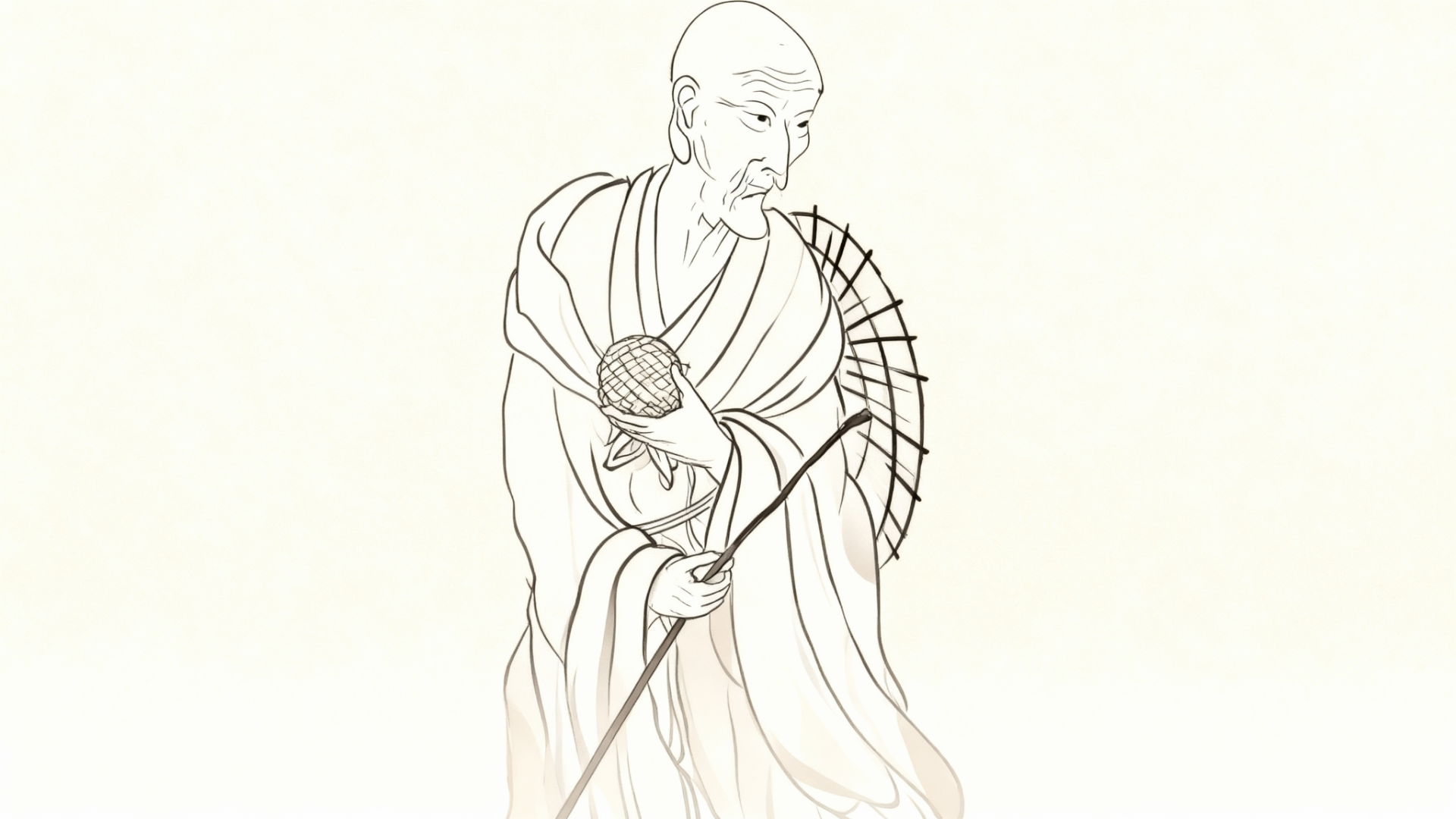
コメント