はじめに
「日本三大悪女」「守銭奴」——長い間、日野富子はこうした否定的なレッテルを貼られてきました。
しかし、近年の歴史研究により、その評価は大きく変わりつつあります。
実は彼女は、崩壊寸前の室町幕府を財政的に支え、11年間続いた応仁の乱の終結にも貢献した「実務型リーダー」だったのです。
本記事では、史料に基づいて日野富子の真の姿に迫ります。
👇noteとYouTubeもどうぞ!
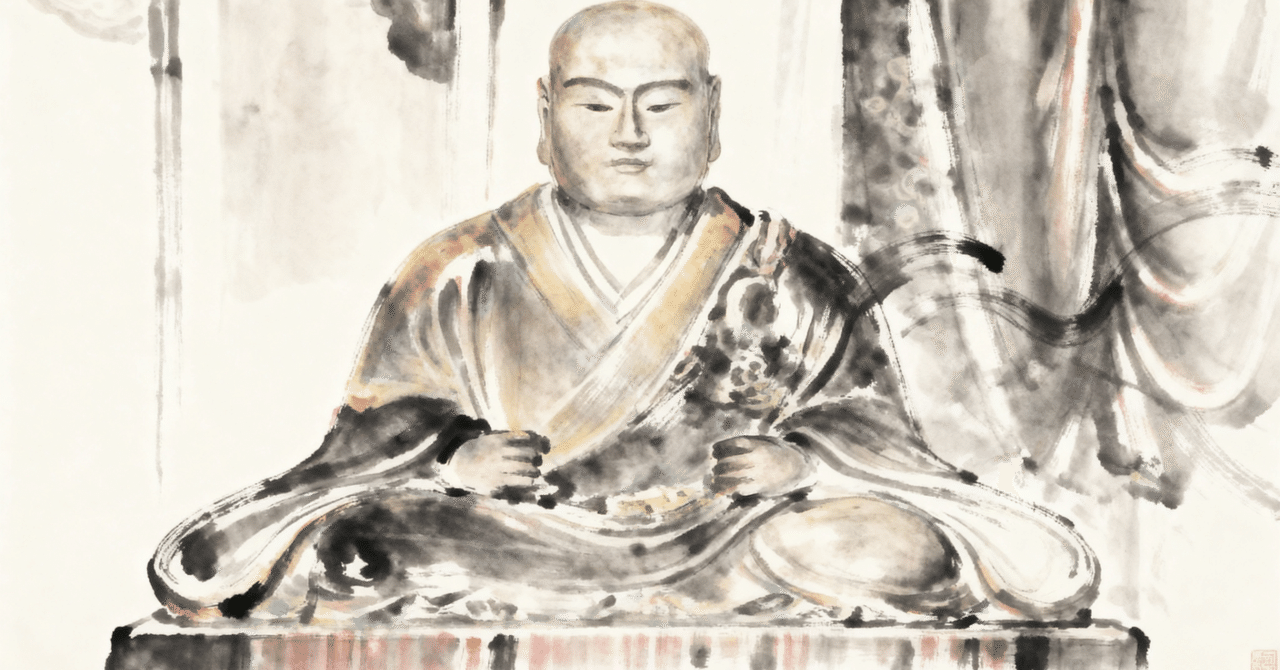
目次
- 日野富子とは誰か
- 室町幕府の財政危機
- 富子による財政改革の実態
- 応仁の乱終結への貢献
- 政治的リーダーシップの発揮
- 評価の変遷:なぜ「悪女」とされたのか
- まとめ
1. 日野富子とは誰か
日野富子は1440年に生まれ、公家の日野重政の娘として育ちました。
1455年、わずか16歳で室町幕府第8代将軍・足利義政の正室となります。
その後、従一位という高い位階を授かり、第9代将軍・足利義尚の母となりました。
彼女が歴史の表舞台に立つのは、夫・義政が政治への関心を失い、文化活動に没頭し始めた後のことです。
義政は1473年に将軍職を9歳の義尚に譲って隠居しましたが、政務への意欲は著しく低下していました。
興福寺の僧侶・尋尊は「将軍は大酒を飲み、諸大名は犬追物に興じている」と痛烈に批判しています。
この政治空白を埋めたのが富子でした。
2. 室町幕府の財政危機
15世紀後半、室町幕府は深刻な財政危機に直面していました。
幕府の主要財源だった京都の金融業者(土倉)や酒造業者への課税は、徳政一揆の頻発により徴収基盤が崩壊しつつありました。
応仁の乱前には月額約200貫文だった納入額は、1496年には月額80貫文にまで激減しています。
義政は美術品を売却したり、寺院の住職職を売ったりして場当たり的に資金を調達していましたが、もはや公式の財政システムは機能不全に陥っていたのです。
3. 富子による財政改革の実態
富子は破綻した幕府財政を立て直すため、複数の革新的な政策を実施しました。
京都七口関の設置
1478年、富子は内裏(皇居)修理を名目に、京都への主要な入口7か所に関所を設け、通行税を徴収し始めます。
この政策は民衆の反発を招き、1480年には徳政一揆が発生して関所が破壊されました。
しかし、富子は直ちに関所を再設置し、幕府財政の維持を優先したのです。
高利貸しと米の投機
富子は東西両軍の大名に対し、月利6%(年利約72%)という高利で資金を貸し付けました。
また、戦時下の米価変動を利用した投機的売買も行っています。
1479年時点で、富子は約7万貫(現代価値で数十億円相当)という莫大な資産を幕府の御蔵に保管していました。
重要なのは、この蓄財が単なる私利私欲のためではなかったという点です。
研究によれば、富子は晩年、火災で焼失した朝廷の御所修復費用を自費で負担するなど、朝廷や幕府の維持に資金を投じました。
彼女の「私財」は、事実上の国家予備財源として機能していたのです。
4. 応仁の乱終結への貢献
従来、富子は応仁の乱の原因を作った張本人とされてきました。
しかし、近年の史料研究により、この通説は完全に否定されています。
軍記物語『応仁記』は富子が山名宗全と結託したと記していますが、同時代の一次史料である『大乗院日記目録』や『経覚私要鈔』にはそのような記述が一切ありません。
乱の真の原因は、畠山家や斯波家の家督争いに有力守護大名が介入したことにあったのです。
むしろ富子は、乱の終結に積極的に貢献しました。
1473年に東軍の細川勝元と西軍の山名宗全が相次いで死去すると、富子は和平工作を主導します。
対立していた足利義政と義視の兄弟を和解させ、西軍の大内政弘には四か国の守護職安堵と官位昇進を約束して京都からの撤退を実現しました。
さらに畠山義就には1,000貫文を提供して退去させ、1477年の乱終結に道筋をつけたのです。
5. 政治的リーダーシップの発揮
富子の政治的影響力は、義政の死後も続きます。
1489年に義尚が25歳で病死すると、富子は義視の子・義材を10代将軍に擁立しました。
さらに1493年の明応の政変では、細川政元と結託して義材を廃し、足利義澄を11代将軍に擁立しています。
当時の記録に「御台一天御計(御台所が天下の全てを取り計らっている)」とあるように、富子は将軍の正室という立場から、実質的な政治的決定権を行使していました。
これは正式な役職に就いたわけではない「非公式な権限」でしたが、富子は日常的な政務の実務を担当し、幕府と朝廷の権威を辛うじてつなぎ止めたのです。
6. 評価の変遷:なぜ「悪女」とされたのか
江戸時代から昭和期まで、富子は「守銭奴」「日本三大悪女の一人」として描かれてきました。
この評価は主に『応仁記』の記述と、同時代の僧侶・貴族による批判的な記録に基づいていました。
しかし1996年以降、史料批判の進展により評価は一変します。
家永遵嗣は「同時代の公家・僧侶の日記には、富子を乱の原因だとする記述が全くない」と指摘しました。
プリンストン大学のThomas Conlanは、『応仁記』が後世に政治的意図を持って著された文書であり、「富子を責任者とする記述は、わかりやすい敵役として創作された可能性が高い」と結論づけています。
現在の学術研究では、富子は「室町幕府の脆弱な財政を支えた実務型リーダー」「応仁の乱終結に貢献した政治家」として再評価されているのです。
まとめ
日野富子は、室町幕府という崩壊しつつあるシステムの延命に成功した、類稀な実務家でした。
彼女の強権的な財政政策は民衆の反発を招きましたが、それは破綻した国家の危機管理を一身に担った結果でもありました。
「悪女」というレッテルは、複雑な政治対立を単純化し、女性の政治参加を否定する当時の価値観が生んだ偏見だったといえるでしょう。
史実に基づけば、富子は政治的空白という未曾有の危機において、利用可能なあらゆる手段を駆使して秩序を維持しようとした、15世紀後半という時代が生んだ傑出した指導者だったのです。
参考文献
- 『大乗院寺社雑事記』臨川書店『増補続史料大成』第26-37巻
- 田端泰子『日野富子 政道の事、輔佐の力を合をこなひ給はん事』ミネルヴァ書房、2021年
- 呉座勇一『応仁の乱 戦国時代を生んだ大乱』中央公論新社、2016年
- Thomas Donald Conlan, “The ‘Ōnin War’ as the Fulfillment of Prophecy,” Journal of Japanese Studies 46:1, 2020年
- 家永遵嗣「足利義視と文正元年の政変」『学習院大学研究紀要』61号、2016年
- 桜井英治「室町幕府財政の発想」東京大学、2000年
- 岡崎嘉彦「軍記物語の女性たち(10)日野富子の生涯―『応仁記』より―」国立国会図書館デジタルコレクション、2014年

コメント