はじめに
90万両という天文学的な借金を抱え、破産寸前だった福井藩。
16歳でこの危機的状況を引き継いだ若き藩主・松平春嶽は、どのようにして藩を立て直し、明治維新を担う人材を輩出したのでしょうか。
身分や出身にとらわれない人材登用、西洋技術の積極的な導入、そして「民を豊かにすることが国を豊かにする」という革新的な経済思想。
春嶽が実践した改革は、単なる一藩の再建にとどまらず、近代日本の国家建設の青写真となりました。
黒船来航という外圧と財政破綻という内憂に直面しながら、果敢に挑戦を続けた春嶽の物語から、現代にも通じるリーダーシップの本質が見えてきます。
👇noteに深掘りし記事を書いています。よろしければこちらもご覧ください!
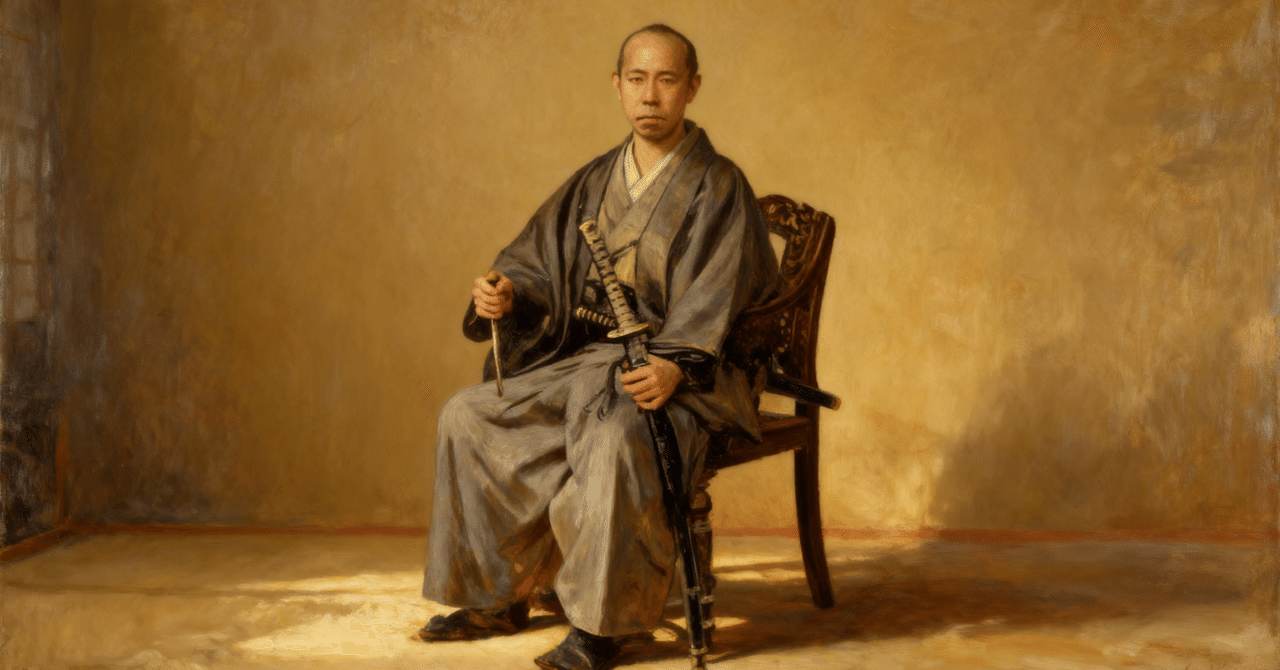
目次
- 絶望的な財政危機からのスタート
- 教育改革―明道館が生んだイノベーション
- 異例の人材登用―橋本左内と横井小楠
- 経済改革―「民富論」の実践
- 軍事の近代化と富国強兵
- 明治維新への遺産
- おわりに
1. 絶望的な財政危機からのスタート
1838年、わずか11歳で福井藩主となった松平春嶽が直面したのは、約90万両という巨額の借金でした。
これは藩の年間収入の数倍に相当する額で、まさに破産寸前の状況です。
当初、春嶽は伝統的な緊縮財政で対応しました。
藩士の給料を3年間半減し、自らの生活費も削減するという厳しい倹約令を次々と発令します。
商人から2万両を借り入れて藩札(藩が発行する紙幣)の信用を維持するなど、応急処置を重ねました。
しかし1853年、ペリー艦隊の来航という衝撃的な出来事が、春嶽の考え方を根本から変えることになります。
西洋列強の軍事力を目の当たりにした春嶽は、もはや倹約だけでは藩も国も守れないと悟りました。
財政再建と軍事力強化を両立させるには、抜本的な改革が必要だったのです。
2. 教育改革―明道館が生んだイノベーション
春嶽の改革の基盤となったのが、1855年に設立された藩校「明道館」です。
従来の儒学中心の教育から大きく転換し、オランダ語、西洋医学、数学(測量・航海術・砲術)など、実用的な学問を積極的に取り入れました。
全部で9科目という幅広いカリキュラムは、当時の藩校としては極めて先進的でした。
特に画期的だったのは、1857年に設置された「洋書習学所」です。
ここでは西洋の書籍を翻訳し、最新の科学技術を学ぶことができました。
また300石以上の藩士とその子どもたち(15~40歳)には月10日の通学が義務付けられ、藩全体の知的水準を底上げする仕組みが作られたのです。
この「和魂洋才」―日本の精神を保ちつつ西洋の技術を取り入れる―という理念は、後の日本の近代化を方向づける思想の先駆けとなりました。
3. 異例の人材登用―橋本左内と横井小楠
春嶽の改革を支えたのは、優れた人材の登用でした。
1857年、わずか23歳の藩医・橋本左内を明道館の学監(校長格)に抜擢します。
左内は「啓発録」を著した俊才で、西洋の知識に通じていました。
彼の指揮下で明道館は飛躍的に発展し、物産科(経済)や兵学科(西洋式軍事学)などの実学部門が次々と設置されていきます。
さらに驚くべきは、1858年の横井小楠の招聘でした。
小楠は熊本藩の藩士で、福井藩とは何の関係もない「よその藩」の人物です。
しかし、春嶽は、その卓越した見識を見抜き、50人扶持(約90石相当)という破格の待遇で政治顧問として迎え入れました。
身分や出身にとらわれずに優秀な人材を登用する。
これは世襲制と藩閥を重んじる当時の社会では前代未聞の決断でした。
春嶽の「能力こそが最も尊重されるべき」という信念は、まさに近代的な人材観の先取りだったといえます。
4. 経済改革―「民富論」の実践
横井小楠がもたらした最大の影響は、経済政策の革新的な転換でした。
小楠は「国是三論」という改革構想で、「富国」「強兵」「士道」の三本柱を提示しますが、その核心は「民を豊かにすることが国を豊かにする」という「民富論」でした。
従来の藩財政は、専売制度や重税によって支配者層が利益を得る仕組みでした。
しかし、小楠は、これを「貨殖の政」(利益追求だけの政治)として批判します。
そうではなく、民衆の生産力を高め、自由な経済活動を促進することこそが真の富国につながると説いたのです。
この理念に基づき、1859年には「物産総会所」が設立されました。
藩が生糸や麻織物などの特産品を一括で買い上げ、長崎や横浜で直接販売する体制を構築します。
オランダ商館との生糸販売契約では、安政6年に25万ドル(約100万両)、翌年には60万ドルもの売上を記録しました。
この改革により、文久期(1861-1864年頃)には藩の金庫に50万両もの正貨が蓄積され、「万年赤字」だった財政は見事に黒字へと転換したのです。
5. 軍事の近代化と富国強兵
経済改革と並行して、春嶽は軍事力の近代化にも積極的に取り組みました。
1857年には武芸稽古所と大砲科を設置し、西洋式の砲術訓練を開始します。
福井藩は洋式大砲の鋳造に成功し、2本マストのスクーナー船「一番丸」を国産で建造しました。
さらにアメリカから軍艦2隻を購入するなど、北陸随一の軍事力を誇るようになります。
これらの軍事改革には莫大な費用がかかりましたが、春嶽は「西洋列強に対抗できる実力を備えなければ独立は守れない」という信念を貫きました。
その成果は、1868年の戊辰戦争で証明されます。
福井藩は洋式装備で武装した精鋭部隊2,034名を新政府軍として派遣し、北越・会津戦争で大きな戦果を上げたのです。
6. 明治維新への遺産
春嶽の改革が育てた人材は、明治維新後の新政府で活躍しました。
由利公正(三岡八郎)は明治政府の財政官僚として「五箇条の御誓文」の起草に参画し、初代東京府知事を務めます。横井小楠が1862年に起草した「国是七条」は、坂本龍馬の「船中八策」や「五箇条の御誓文」の原型となったとされ、明治国家の基本理念に大きな影響を与えました。
また、明治4年には藩校が「明新館」と改称され、一般の民衆にも開放されます。
アメリカ人教師グリフィスを招いて最先端の化学実験を行うなど、約800名の生徒が学ぶ近代教育機関へと発展しました。
春嶽の「民を富ませることが国を富ませる」という理念、能力主義的な人材登用、そして西洋技術の積極的導入は、明治日本の近代化政策そのものの雛形となったのです。
おわりに
松平春嶽の藩政改革は、必ずしも完璧な成功を収めたわけではありません。
明治維新直前の福井藩は依然として多額の債務を抱えており、軍備拡張の費用負担も重くのしかかっていました。
しかし、絶望的な財政危機と外圧という二重の困難に直面しながら、春嶽が示した先見性とリーダーシップは特筆に値します。
教育・経済・軍事を一体として改革し、身分を超えて優秀な人材を登用し、「公議」に基づく政治を追求した姿勢は、現代のリーダーにも多くの示唆を与えてくれます。
「衆言を聴きて宜しき所に従う」―多くの意見に耳を傾け、良いものを採用する―という春嶽の信念は、変革の時代を生き抜く知恵として、今なお輝きを失っていません。
参考文献
- 『福井県史』通史編4近世二 第六章(福井県史編さん委員会、1996年)
- 「幕末期福井藩の殖産興業策と財政について」本川幹男(2016年)
- 「幕末維新期の福井藩政改革と藩校」船澤茂雄(2011年)
- 『横井小楠』人物叢書(圭室諦成著、吉川弘文館、1967年)
- 『国是三論』横井小楠著、花立三郎全訳注(講談社学術文庫、1986年)
- 福井市立郷土歴史博物館「展示解説シート No.107, 115, 131, 170」(2018-2024年)
- 『逸事史補』松平春嶽(明治3-12年、福井市立郷土歴史博物館所蔵)
- 国立国会図書館「近代日本人の肖像」

コメント