はじめに
今から370年前の1654年、フランスの数学者ブレーズ・パスカルとピエール・ド・フェルマーが交わした数通の手紙が、世界を変える数学革命の始まりでした。
きっかけは、ある賭博師の素朴な疑問。
「中断されたゲームの賞金を、どうやって公平に分けるべきか?」この問いから生まれた確率論は、現代のAI技術やデータサイエンス、金融工学の基礎となっています。
皆さんにも身近な「確率」という概念が、どのようにして生まれたのか、その驚きの物語をお届けします。
👇noteに深掘りした記事を書いてます。よろしければこちらもどうぞ!
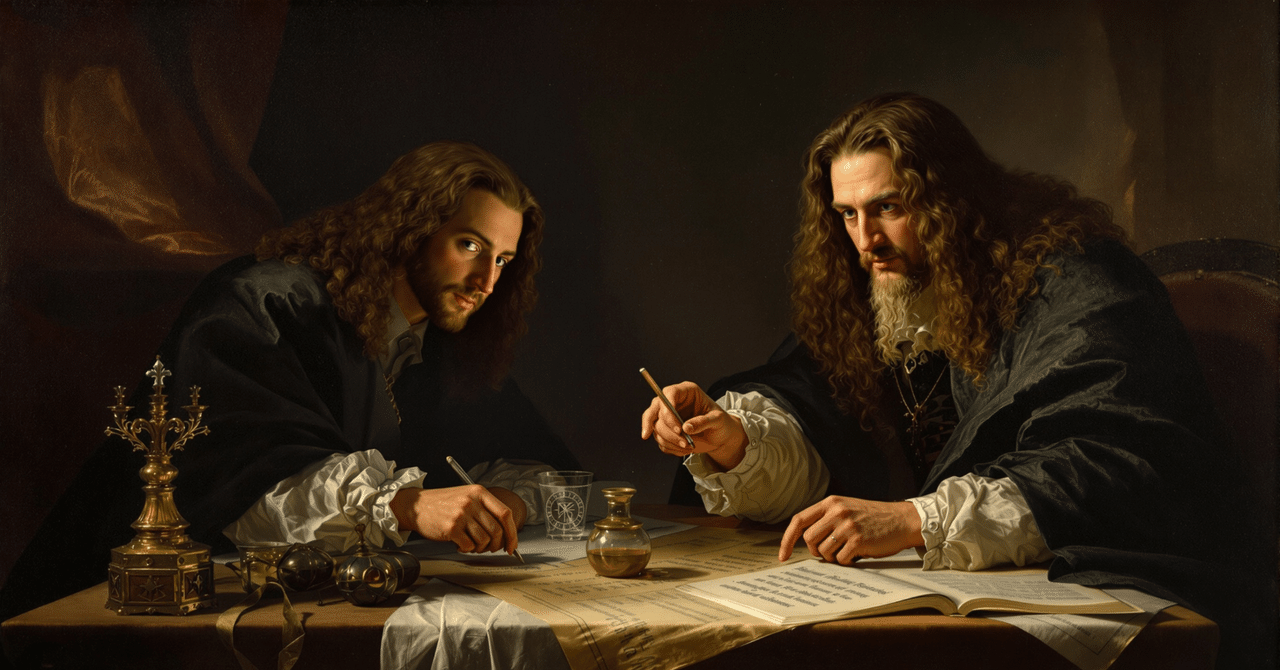
目次
1. 賭博師の疑問から始まった数学の革命
17世紀のフランスは、絶対王政の太陽王ルイ14世の時代でした。
宮廷では華やかな文化が栄え、貴族たちの間で賭博が盛んに行われていました。
公式には賭博は禁止されていましたが、王は政治的な理由から宮廷での賭け事を黙認していたのです。
そんな中、アントワーヌ・ゴンボー(通称シュヴァリエ・ド・メレ)という人物がいました。
彼は貴族であり文筆家でもありましたが、何より熱心な賭博師として知られていました。
ド・メレは単なるギャンブラーではありません。
賭け事の背後にある数学的な法則に強い関心を持ち、自分なりに計算を試みる知的好奇心の持ち主でした。
しかし、ある日ド・メレは困った問題に直面します。
自分の計算では有利なはずの賭けで、なぜか負けが込んでしまうのです。
そこでド・メレは、当時フランス最高の知性とされていた数学者ブレーズ・パスカルに助けを求めました。
この出会いが、確率論という新しい数学分野の誕生につながったのです。
2. シュヴァリエ・ド・メレの二つの難問
ド・メレがパスカルに持ち込んだ問題は二つありました。
サイコロ問題
最初の問題は、サイコロの確率に関するものでした。
- ゲーム1:1個のサイコロを4回投げて、少なくとも1回は6の目が出ることに賭ける
- ゲーム2:2個のサイコロを24回投げて、少なくとも1回はダブルシックス(両方とも6)が出ることに賭ける
メレの推論では、試行回数の比率と確率の比率が釣り合っているので、両方のゲームは同じように有利なはずでした。
ところが実際には、ゲーム1では勝てるのに、ゲーム2では負けが込んでしまいます。
分点問題(点数の問題)
もう一つは、より深刻な問題でした。
二人のプレイヤーがそれぞれ32ピストル(当時の通貨)を賭けて、先に3点取った方が総額64ピストルを獲得するゲームを考えます。
ところが、Aが2点、Bが1点の時点でゲームが中断されてしまいました。
この場合、64ピストルをどのように分配するのが最も公正でしょうか?
従来は現在の得点比で分配していましたが、これでは残りのゲームでの勝利可能性を全く考慮していません。
明らかに不公平です。
3. パスカルとフェルマーの天才的解法
1654年7月、パスカルはトゥールーズの高等法院で働く数学者ピエール・ド・フェルマーに手紙を送り、この問題について相談しました。
二人は数か月にわたって書簡を交わし、それぞれ異なるアプローチで同じ結論に達したのです。
フェルマーの組み合わせ論的解法
フェルマーは、中断されたゲームを最後まで続けた場合に起こりうる全てのパターンを数え上げる方法を考えました。Aがあと1勝、Bがあと2勝必要な状況では、最大2回の勝負で決着がつきます。
可能な結果を分析すると、Aが最終的に勝利するパターンは3通り、Bが勝利するパターンは1通りです。
したがって、賞金は3:1の割合で分配すべきということになります。
パスカルの再帰的解法と期待値の発明
パスカルは全く違うアプローチを取りました。
彼は「次の一回の勝負で何が起こるか」に注目したのです。
次の勝負でAが勝った場合:Aの完全勝利で64ピストル獲得
次の勝負でBが勝った場合:2対2の同点となり、32ピストルずつ分配
それぞれの確率は1/2なので、Aの「期待される」取り分は: (64 × 1/2) + (32 × 1/2) = 48ピストル
この計算結果は、フェルマーの方法と完全に一致しました。
パスカルが使った考え方は、現代でいう「期待値」の概念そのものです。
不確実な未来の結果を、その起こりやすさで重み付けして平均する。
この革新的なアイデアが、確率論の中核をなすことになります。
4. 確率論の誕生とホイヘンスの貢献
パスカルとフェルマーの発見は、最初は私的な書簡交換にとどまっていました。
この新しい知識を学問として体系化したのが、オランダの科学者クリスティアーン・ホイヘンスです。
1655年にパリを訪れたホイヘンスは、二人の研究について聞き及び、オランダに帰国後に自力で問題を解きました。
そして1657年、史上初の確率論教科書『賭博における計算について』を出版したのです。
ホイヘンスの最大の貢献は、パスカルが暗黙のうちに使っていた「期待値」の概念に、明確な定義と名前を与えたことでした。
この三段階のプロセス──実践家からの問題提起(ド・メレ)、天才による発明(パスカル・フェルマー)、体系化と普及(ホイヘンス)──は、科学的発見の典型的なモデルを示しています。
5. 現代社会への驚くべき影響
確率論の誕生は、単に数学の一分野が生まれただけではありませんでした。
それは人類の思考様式に根本的な変革をもたらしたのです。
パスカルの期待値概念は、現代の金融工学の基礎となっています。
保険会社が保険料を計算するのも、投資家がリスクを評価するのも、すべてこの考え方に基づいています。
1973年のブラック・ショールズ・モデル(ノーベル経済学賞受賞)も、パスカルの期待値理論の直接的な発展形なのです。
現代社会で注目されるビッグデータ解析や機械学習も、確率論なしには成り立ちません。
Googleの検索アルゴリズムも、自動運転車の判断システムも、医療診断のAIも、すべて確率的な推論に基づいています。
特に重要なのは、AIの分野で中心的な役割を果たすベイズ統計学です。
これは新しい情報が得られるたびに、予測の確率を更新していく手法で、まさにパスカルたちが始めた「確率を用いて推論する」という思想の延長線上にあります。
20世紀になると、確率論は物理学の根幹にまで影響を与えました。
量子力学では、粒子の位置や運動量を確率的にしか予測できないことが明らかになり、「神はサイコロを振らない」と言ったアインシュタインと、確率論的解釈を支持するボーアとの間で、科学史上最も有名な論争が繰り広げられました。
まとめ
シュヴァリエ・ド・メレがサイコロの目に頭を悩ませた素朴な疑問から始まった知の探求は、370年の時を経て、私たちの生活のあらゆる場面に影響を与えています。
スマートフォンの音声認識も、SNSのおすすめ機能も、天気予報も、すべて確率論の恩恵を受けているのです。
パスカルとフェルマーの功績は、偶然を科学の対象にしたことでした。
それまで運命や神の意志とされていた「偶然」に、厳密で普遍的な数学的法則があることを初めて示したのです。
現代のデータ駆動型社会そのものが、1654年夏のパリで始まった知的革命の直接的な産物なのです。
参考文献
- Œuvres de Fermat, Vol. II (Tannery, Paul and Henry, Charles編, 1894)
- “Pascal and Fermat Devise the Theory of Probability” EBSCO Information Services
- De ratiociniis in ludo aleae (Christiaan Huygens, 1657)
- “The Pascal-Fermat correspondence: How mathematics is really done” (Richard Ressman, 2010)
- 確率についての書簡 (岡部毅, 高松大学, 2021)
- フランス国立図書館「Évocation d’Antoine Gombault (chevalier de Méré)」
- フランス科学アカデミー「Pascal et Fermat : leur correspondance aux origines de la théorie des probabilités」

コメント